ミカドの帝国
アメリカ人の「お雇い外国人」第1号で最も初期のジャパノロジストとして知られるウィリアム・エリオット・グリフィスがThe Mikado’s Empire: A History of Japan from the Age of Gods to the Meiji Eraの「注釈と補遺(Notes and Appendices)」(注:同書は1876年の初刊以来、数度に渡って増補・改訂がなされており、生麦事件に関する記載を含むThe Bombardment of Kagoshimaは1886年刊行の第5版以降は削除されています。また同書の第2部を訳出した山下英一訳/東洋文庫版『明治日本体験記』では「注釈と補遺」そのものが割愛されています。英語版にも日本語版にも該当する箇所が見当たらないという問い合わせがあったので、補足しておきます。↓に引用しているのも筆者が英語版の第1版より訳出したものであることを明記しておきます)で生麦事件に関連してこんなことを書いている――
……江戸の当局者は事前に外国人に対し、当日は東海道の通行を控えるよう求めていた。しかし彼らは傲慢にも、そして国家的苦難に対する思いやりの言葉や同情心もなく、これを拒絶した。2人のアメリカ人紳士、E・ヴァン・リード氏とF・ショイヤー氏は、同じ日(1862年9月14日)の午後、乗馬中に島津一行に遭遇した。そして行列を避け、何の支障もなくその場を通過した。
生麦事件当日、被害に遭ったイギリス人たちよりも少しばかり早く島津久光一行の行列に遭遇した外国人がいたものの、ちゃんと日本の流儀に従って下馬して行列を見送ったためにトラブルに巻き込まれることはなかった――。この事実については比較的よく知られていて、しかもその外国人とはユージン・ミラー・ヴァン・リードという人物であったことも概ね周知の事実と言っていい(アーネスト・サトウが『一外交官の見た明治維新』で書いている他、西園寺内閣で外務大臣や逓信大臣を務めた林董が『後は昔の記』に当のヴァン・リードのコメントも交えて書いている。曰く「日本の風を知らずして倨傲無礼の為めに殃を被りたるは、是れ自業自得なり」)。ただ、ウィリアム・エリオット・グリフィスが記すところによれば、この時、ヴァン・リードは1人ではなかった。1人の同伴者がいたのだ。それが「F・ショイヤー氏」――ということになるわけだけれど、この「F・ショイヤー氏」って何もの?
いや、別にそんなの、どうでもいいでしょう? というのが大方の反応かな。しかし、ワタシにとってはそうではない。というのも、戊辰戦争当時の駐日アメリカ公使であるロバート・ブルース・ヴァン・ヴァルケンバーグが本国の国務長官、ウィリアム・スワードに宛てた1868年2月7日付け至急報告の中にE・A・ショイヤーという人物が登場するのだ。備前藩兵と英米仏の海兵隊や警備兵との間で銃撃戦に発展した「神戸事件」当時、ヴァン・ヴァルケンバーグに「個人秘書」として仕えていた人物。
私の護衛の海兵隊員がプロイセンの代理公使、マックス・フォン・ブラントと私の個人秘書、E・A・ショイヤーとともに真っ先に後を追いました。私は居留地に残り、海兵隊が上陸すると約75名の1中隊を榴弾砲1門とともに敵を追跡中の米英仏部隊の支援のために急派しました。私は残る中隊を三つに分け、その一つは兵庫通りから居留地への立入を規制するために榴弾砲1門とともに派遣し、もう一つはわれわれの右翼からの側面攻撃に備えさせました。そして残りはアメリカ領事館のある海浜に配置しその方面からの攻撃に備えてパトロールさせました。イギリスの艦隊からは約300名の水夫と海兵隊員が2挺のライフル銃とともに上陸しました。またフランス兵は約50名でした。われわれは半時間、約500名で通りを封鎖し、敵を追撃しました。敵は退却し、荷物を投げ捨て、散り散りになって丘へ向かいました。
「F・ショイヤー氏」がここに登場するE・A・ショイヤーと何らかの血縁関係にあるのは間違いない。さらに言えば、生麦事件当時、横浜にはラファエル・ショイヤーという人物もいた。横浜開港資料館刊行の『横浜もののはじめ考』によればニューヨーク生まれのユダヤ人とかで、1860年に来日。居留民からは「ショイヤー老人」と敬われ、1865年には居留地参事会の初代議長にも選ばれている。またこの「ショイヤー老人」の妻がアナで、夫の死後、ヴァン・ヴァルケンバーグと再婚することは『「東武皇帝」即位説の真相 もしくはあてどないペーパー・ディテクティヴの軌跡』にも記した通り(このアナというのが思いの他、興味深い人物で、どうせリンクをクリックしてくれる人はほとんどいないだろうから、一点だけここに書き記しておくと、かの高橋由一が著した「高橋由一履歴」に油絵の手ほどきを受けた人物として出てくる。曰く「文久三年米國シヤウヤノ婦人ナル畫家夙ニ横濱ニ居留セリ或時惑滿師ノ照會ヲ得テ該婦人ノ居館ヲ訪ヒタルニ折節不在ナリシガ切ニ請フテ婦人ノ揮寫セル油繪數面ヲ觀覽セシニ」云々。この「シヤウヤノ婦人」が後のアメリカ公使夫人とは、はたしてどれほどの日本人が知っているものか……?)。こうなると「F・ショイヤー氏」はヴァン・ヴァルケンバーグとも少なからぬ接点を有しているわけで、それが一体どういう人物だったのかは自ずと関心事項とはなる。
で、これについてまず最初に有力な情報を提供してくれたのはヴァン・ヴァルケンバーグの1代前の駐日公使であるロバート・プライン(なお、この人物をめぐっては一般に「ロバート・プルイン」という表記が採用されているのだけど、ファミリーネームのPruynはPrineと発音することがWikipedia英語版に記されている。また当時の史料でも「プライン」と表記しているものが少なくない)。そんなロバート・プラインがウィリアム・スワードに宛てた1862年9月18日付け至急報告によれば、「F・ショイヤー氏」はフランク・ショイヤーという名前で、生麦事件当時、なんと14歳の少年だったというのだ。しかも事件後、当時、成仏寺に住んでいた米国長老派教会の宣教師で医師のヘップバーン(一般には「ヘボン」の名で知られる)を呼びに行っているのだ。
嬉しいことにわずか14歳のアメリカ人の少年、フランク・ショイヤーが薩摩藩士たちの中をかき分けヘップバーン博士の住居まで4分の1マイル以上も歩いてくれたお陰ですぐに博士が負傷者の元に駆けつけることができたのです。
生麦事件当日、ヘップバーンが当時、アメリカ領事館が置かれていた本覚寺で負傷者の治療に当たったことはよく知られているんだけど、成仏寺までヘップバーンを呼びに行った人物がいて、それが14歳の少年で、しかも当人もその場に居合わせて事件を目撃していたという事実は全く知られていない。
しかし、ウィリアム・エリオット・グリフィスが言う「F・ショイヤー氏」が実は14歳の少年だったとすると、ラファエル・ショイヤーもしくはE・A・ショイヤーの子どもだったという可能性が出てくる。実際、『横浜もののはじめ考』ではラファエル・ショイヤーについて「万延元年正月、妻子とともに六〇歳で来日した」。もし仮にフランクがラファエル・ショイヤーの子どもだったとしたら、ヴァン・ヴァルケンバーグにとっても義理の息子ということになるわけで、この時点でいよいよワタシのこの人物に対する興味は高まったと言っていい。
そして、遂に決定的な情報に遭遇した。情報を提供してくれたのはCharles Lawというカナダの作家が書いたProgeny Unbound: Peace Be to This Houseという本。いわゆる「ファミリー・サーガ」と呼ばれるジャンルのもので、全5冊からなるシリーズのこれが最終巻。描かれているのはアーロン・ハートという人物を始祖とする一族で、何でも1724年にロンドンで生まれたユダヤ人なんだそうだけど、カナダに渡って毛皮貿易などで財を成し遂には一大ダイナスティを築き上げた。第1巻ではそのアーロン・ハートの物語を綴り、第2巻から第4巻まではその3人の息子を、そして第5巻ではさらにその子孫たちを――と、まさに一大サーガと言うしかないような構成。まあ、向こうはこういうのが盛んだからね。向こうにあってこっちにないものの一つがこのファミリー・サーガという文学ジャンルだと思う。ともあれ、この「ハート・ダイナスティ」シリーズの第5巻にラファエル・ショイヤーのことが記されているのだ。アーロン・ハートの3男で第4巻、Brother Benjamin: A Man for Confrontationの主人公、ベンジャミン・ハートの長女フランシスの夫がラファエル・ショイヤー。さらに本の冒頭にはハート一族を彩る人物たちの詳細な系図が示されているのだが、Children of Banjamin Hartとして――
Frances Hart
(1807-1849)=Raphael Schoyer
(1800-1865)Banjamin Hart (1836) David Arthur (1889) Ernest Augustus (1843) Albert Asher (1845) Frank Reuben (1848)
本文を読むと、フランシスが生んだ5人の子どものうち、最初の2人は早世したこと、フランシス自身も5人目を生んだ際、産後の肥立ちが悪く亡くなったことなども記されていて、大変な情報の宝庫。ただフランシスの死後、ラファエル・ショイヤーはアナと再婚することになるわけだけど、それがいつのことかまではさすがにこの本には記されていない。
ともあれ、こうして1862年9月14日、当時の武蔵国橘樹郡生麦村で発生した惨劇において被害に遭ったイギリス人たちよりも少しばかり早く島津久光一行に遭遇していた「2人のアメリカ人紳士」とは、1人はユージン・ミラー・ヴァン・リードであり、もう1人はラファエル・ショイヤーの5男、フランク・リューベン・ショイヤーであったことがはっきりしたわけだけど……結局、ワタシは『「東武皇帝」即位説の真相 もしくはあてどないペーパー・ディテクティヴの軌跡』にはアーネスト・オーガスタス(E・A・ショイヤー)のことのみを記してフランクのことは記さず。「東武皇帝」即位説とは直接、関係のないことなので。でも1862年9月14日、1人の少年が身も凍るような恐怖に震えつつ、それでも勇気を振り絞って「薩摩藩士たちの中をかき分け」、成仏寺まで駆けた(ロバート・プラインは「歩いた」と書いているのだけど、ここは「駆けた」でしょう)のは紛れもない事実。きっとフランクは生涯、この日の出来事を忘れなかっただろう。14歳の晩い夏に「ミカドの帝国」で経験した生涯最大の冒険を……。
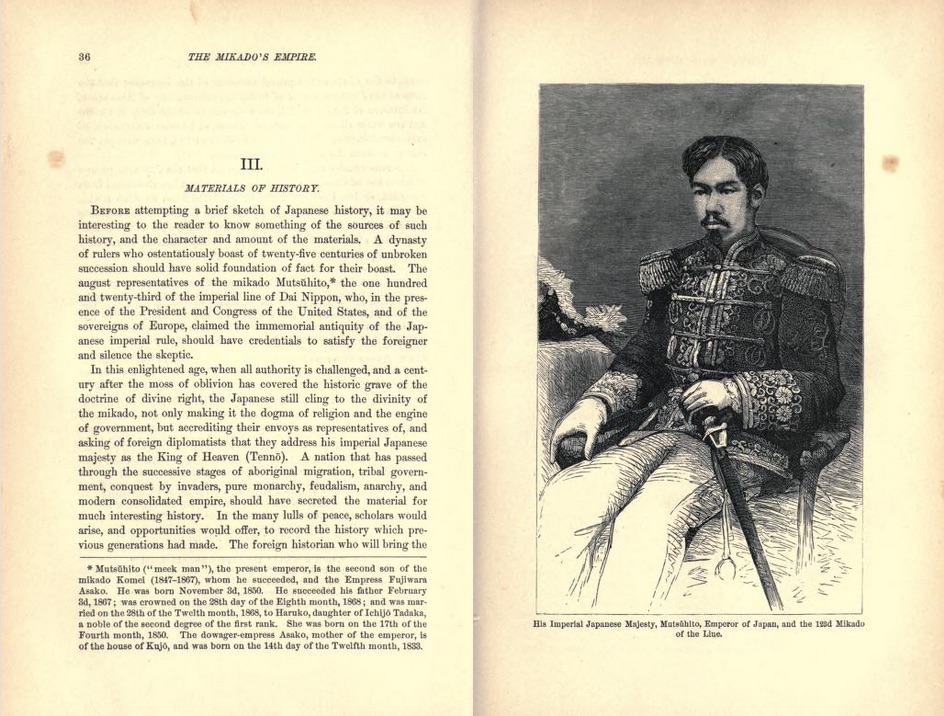
About Me
On PW_PLUS
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」①
- ◦ある不良外国人に捧げる「時の娘」②
- ◦我それを偏見と言う。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル①〜
- ◦保護者と被保護者のソネット〜1ダースのペーパーバック・オリジナル②〜
- ◦本の名は。〜1ダースのペーパーバック・オリジナル③〜
